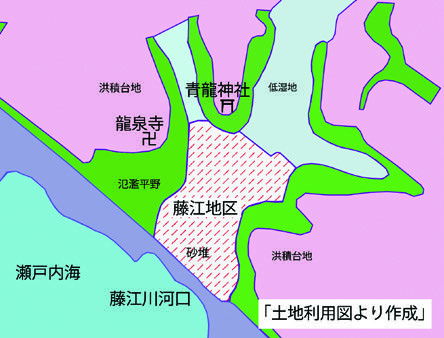人丸
【まめ知識03】明石郡の官庁街
明治12(1879)年に郡区町村編制法が兵庫県で施行され行政区画として発足した明石郡は全域が旧明石藩領で、明治22(1889)年の時点で明石町、林崎村、大久保村、魚住村、伊川谷村、玉津村、櫨谷村、押部谷村、平野村、神出村、岩岡村、垂水村の1町11村でした。相生町には明石郡の警察署、電信局、治安違罪裁判所、郡役場、公会堂など次々と移転新築され、郡の一大官庁街となりました。相生町は、この地域の先進地であった明石城下と大蔵谷村の中間点であり、民家も比較的に密集していなかったことで移築や新築が容易であったことが推測されます。郡制には郡長(官選)と郡会・郡参事会が設けられ自治体として機能しておりましたが、町の単位、県の単位も存在していたため、行政区分が煩雑でした。やがて各村は併合を繰り返し、明石市、神戸市などに統合され、郡制は大正12(1923)年に廃止されました。明石市の初代市長は明石郡最後の郡長の三輪伸一郎氏で、彼は明石市の理想は庭園的住宅都市の建設であると述べていました。